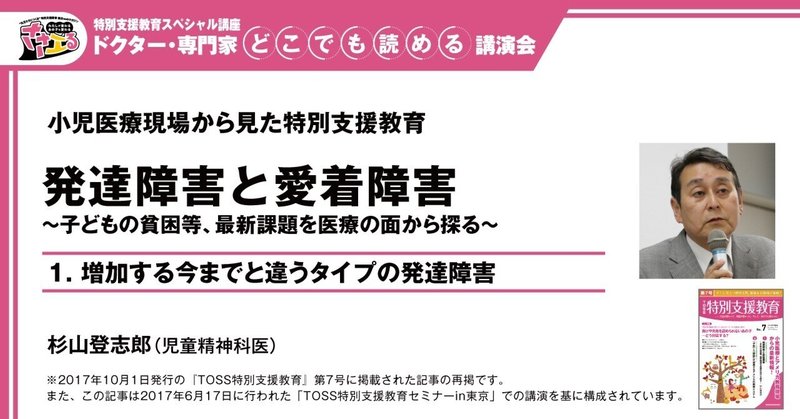
発達障害と愛着障害〜子どもの貧困等、最新課題を医療の面から探る~①増加する今までと違うタイプの発達障害
杉山登志郎(児童精神科医)
1、増加する今までと違うタイプの発達障害
これから愛着障害についてお話しします。
今、学校現場では発達障害への対応だけでは上手くいかないケースが増えてきました。今までの方法で対応が可能だった分かりやすい発達障害は一体どこにいってしまったのかと思います。私の外来でもそのようなケースが増えています。
診療に来る子どもは、だいたい家庭に問題を抱えていることが多いです。ときどき、核家族でご両親が離婚していない、家庭に問題がなさそうな子どもが診療にくると、えっ、どうして? と思います。言い方が乱暴ですが今は複雑な問題を抱えた強者ぞろいの外来になっています。
さて、ここで基本的な発達障害の一覧を表示しましたが(下画像1参照)、これは説明を省略させていただきます。TOSSの先生でしたら、基本的なことから説明しなくても大丈夫ではないでしょうか。

ただ、この一覧の一番下に記載した「愛着形成と情動コントロールの発達」は、子ども虐待とか愛着障害のケースです。結局、愛着障害は、子ども虐待と子育て困難をきたしている場合に、愛着形成に問題が起きてきてしまって、そこから複合的な問題になるということです。それと発達障害が非常に複雑に絡み合っています。そのような発達障害のケースの子どもと保護者が、学校現場で先生方を悩ませることになっています。
こういった発達障害は、次の「多因子モデル」(上画像2参照)で説明します。
多因子モデルというのは、一つの病気の原因が一つの遺伝子の異常で起きるのではなく、およそ20から30の遺伝的な素因が積み重なっていき、病気のラインを越えてしまうモデルです。
最近よく言われているのが、個々の遺伝的な素因の中に、環境因が入ることです。今、言われている子どもの貧困の問題も、この環境因の中に入れていいと思います。
私は、この貧困の問題と発達障害が絡み合っていることについて、数年前まではまったく念頭に置いてもいませんでした。ところが、実際に外来で子どもたちや親を診療し、様々な症例を経験すると、貧困が子どもの発達障害に絡まざるを得ないことに、否応なしに気付かされました。それには愛着障害が当然絡むわけです。そこを今日のセミナーにいらした先生方に説明できればと考えています。

「発達障害を巡る誤解と偏見」(上画像3参照)。これについて簡単に説明しますと、まず発達障害は固定的なものではないということです。つまり昔の発達障害の概念とは根本的に異なるということです。そして発達障害の認知特性はマイナスではありません。そうでなかったら、発達障害を持つ子どもが増えるはずがないのです。
特に自閉スペクトラム症は、社会的な苦手さからくるものですよね。社会的な苦手さを抱えるハンディキャップを持っていたら結婚ができないですよ。結婚ができなかったら子どもが増えないですよね。そうすると発達障害を持つ子どもは減っていくはずなのにすごい勢いで増えてきている。今は学校の先生の中にも多くいらっしゃいます。
結局、増えているのは発達の特性がマイナスではないからです。それから通常なら発達障害は症状が年々良くなってきます。特に小学校の時期というのは黄金時代です。毎年良くなっていくのが普通です。
もし、そこで悪くなったとしたら、これは教育に何か問題があるかもしれないと振り返る必要があります。そうではなくても、そこに愛着の問題が絡むとおかしくなるというのが今日のテーマです。それから発達障害の症状にはジャンプして良くなっていく年齢があります。小学生でいいますと9歳10歳のところです。
神経の選定が終了して、神経の伝達速度が上がったところで、今まではハードルに引っかかっていたかのようにできなかった問題が急にできるようになります。
発達障害の治療は教育です。医療はあくまでも側面援助です。そして今回、愛着障害を取り上げる理由は、単純な発達障害に比べてひねりが入った反応を示す子どもがいるからです。
その一例として、何かを提案しても「ダメ! イヤ! やらない!」と最初からネガティブな反応の子ども。「分かった」とか「うん、やってみる」といった素直な反応が出てこない子ども。ほかの子どもたちとまったく協調ができない子どもがいます。
先日、小学3年生のあるクラスでお別れ会を企画したそうです。クラスのうち、ほぼ全員がお別れ会で「これをやろう」と意見が一つにまとまったのですが、1人だけ頑としてそれはイヤだと拒否した子どもがいたのです。そのクラスはどうなったかというと、子ども同士で乱闘になったそうです。その「やろう」といった子どもの中にアスペルガー症候群の子どもがいました。その子が、私の外来で「僕じゃなくて反対したあの子がここに診察に来ればいいのにね」と言っていました。
その他には、平気でうそをつく子ども。自閉スペクトラム症(ASD)の子どもも平気で嘘をつきますが、愛着障害が絡んでいる子どもは嘘のレベルが違います。大人が思わず信じてしまうような嘘をついたりします。また、落ち着きがなく常にイライラしている子どもや叱られるとフリーズをする子どももいます。
(2.発達障害と密接に関わる愛着障害 へ続く)
杉山登志郎
久留米大学医学部卒業後、同大学医学部小児科学教室、名古屋大学医学部精神医学教室に入局。その後、愛知県心身障害者コロニー中央病院精神科医長などを務め、カリフォルニア大学ロサンゼルス校神経精神医学研究所に留学。帰国後、静岡大学教育学部教授、あいち小児保健医療総合センターの心療科部長兼保健センター長、2010 年より浜松医科大学児童青年期精神医学講座特任教授、2017 年より福井大学こどものこころの発達研究センター児童青年期こころの専門医育成部門客員教授。
※この記事は2017年10月1日発行の『TOSS特別支援教育 第7号』に掲載されたものの再掲です。
また、この記事は2017年6月17日に行われた「TOSS特別支援教育セミナーin東京」での講演を基に構成されています。
一部、名称等が当時のものになっていることがありますこと、あらかじめご承知おきください。
※この記事へのお問合せはTOSSオリジナル教材HPまで。
https://www.tiotoss.jp/


