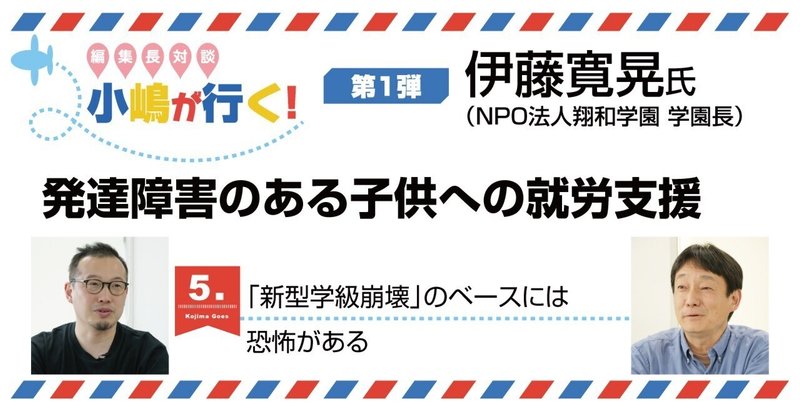
<有料マガジン・メンバー無料>編集長対談 小嶋が行く! 第1弾:NPO法人翔和学園 伊藤寛晃学園長 【第5回 「新型学級崩壊」のベースには恐怖がある】
「ささエる」の小嶋悠紀編集長が、様々な人たちと特別支援に関する対談をするコーナーが始まりました。
第1弾の対談相手はNPO法人翔和学園の伊藤寛晃学園長。
この対談のテーマは「発達障害のある子供への就労支援」です。
第5回は「「新型学級崩壊」のベースには恐怖がある」です。
※有料マガジンですが、夏休み第1弾ですので、今回の記事は無料でお読みいただけます。
※続きはマガジンを購入いただくか、「ささエる」メンバーシップ(月額600円)にご登録いただくとお読みいただけます。(6-9月連載)
※記事の最後に続きの対談風景の動画を収録しています。
小嶋 最近、「新型学級崩壊」という言葉をよく耳にします。本当は十数年前からある言葉なんですが。新型学級崩壊というのは、力のある先生が、黄金の3日間とか、そういうことに対して、今までのセオリー通りにちゃんとやれてるのに、一気に崩れていくような、そういう現象です。実際、僕も他の先生のクラスで目の当たりにしたことがあります。そういうのも、やっぱりコミュニケーション的なところが関連していたり、また、何か違う要因があるのかなと思うんですが、どうですか?

伊藤 ベースにあるのが、安全と恐怖の「恐怖」です。今までうまくいってきてプライドが高いと、うまくいかないことへの恐怖や、うまく起こるはずのことが起きなかったり、起きるはずのないことが起きたりすることへの恐怖。そこを、私たちは、ある種、楽しんだりとか、「おおっ、こう来るか」と、「今年はなんか違うことやってみようかな」とか思いますよね。
小嶋 柔軟性ってことですね。
伊藤 はい。そこがもしかすると、「恐怖」を中心としている。そうすると目の周りの表情や声のトーン、高さとか抑揚の合図が出る。子供たちはその合図を絶対に一瞬で見取ります。「ああ、この人は敵だ、味方ではない」と。そうすると、子供たちも、また防衛反応として。

小嶋 出しますものね、行動を。
伊藤 つまり、どちらも恐怖をベースに自己防衛をしているのに、相手にとっては攻撃に見える。
小嶋 見えるんです(笑)。
伊藤 これが、今、小嶋先生がおっしゃったような図式なんだと思います。
小嶋 そうですね。
伊藤 そして、この対談の冒頭で小嶋先生がおっしゃっていた、「粘り強さがないと社会人になって苦労する」ということについても、これは、私たち教師も一緒だと思います。
小嶋 なるほど、そうですよね。だから、本当に僕たち自身も、柔軟でしなやかであって、粘り強くその子供たちに向き合っていって、しかも、笑顔で自己開示をしながらコミュニケーションを誘っていくっていうのが、自然とできていたほうがいいわけです。それが遠回りなように見えても、結局、最終的に発達障害の子たちが就労というところに結びついていく、すごく大事なポイントなんだと、今、お話を聴いていて思いました。
(6,「しかめ面で育てられたら防衛的になる」に続く)
この対談の続きを少しだけ動画で公開いたします!
気になった方は、ぜひ、メンバーシップにご登録ください。
伊藤寛晃
1969年生。中央大学文学部卒業。学生時代に経験した大工見習いを卒業も継続。その後、かねてからの夢だった教師の夢を諦めきれず一念発起。塾講師、サポート校の教師を経て、2002年から『翔和学園』に勤務。2013年秋に学園長に就任。
NPO法人翔和学園 https://showa-gakuen.net/
小嶋悠紀
本誌編集長・元小学校教諭
(株)RIDGE SPECIAL EDUCATION WORKS 代表
大学当時より発達障害の青年たちの余暇支援活動団体を立ち上げ発達支援に関わる。卒業後、特別支援を要する子供たちへの支援を中心に講演活動を行う。長野県養護教諭研究協議会において、全県の幼・小・中・高・特の1000名の養護教諭に特別支援の講演を行う。NPO法人長野教師力向上NETでも発達支援者育成部門を担当。
※この記事へのお問合せはTOSSオリジナル教材HPまで。
https://www.tiotoss.jp/
© 2023 TOSS,The Institute for Teaching-Skill Sharing.Printed in Japan


